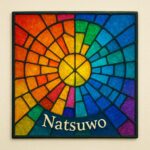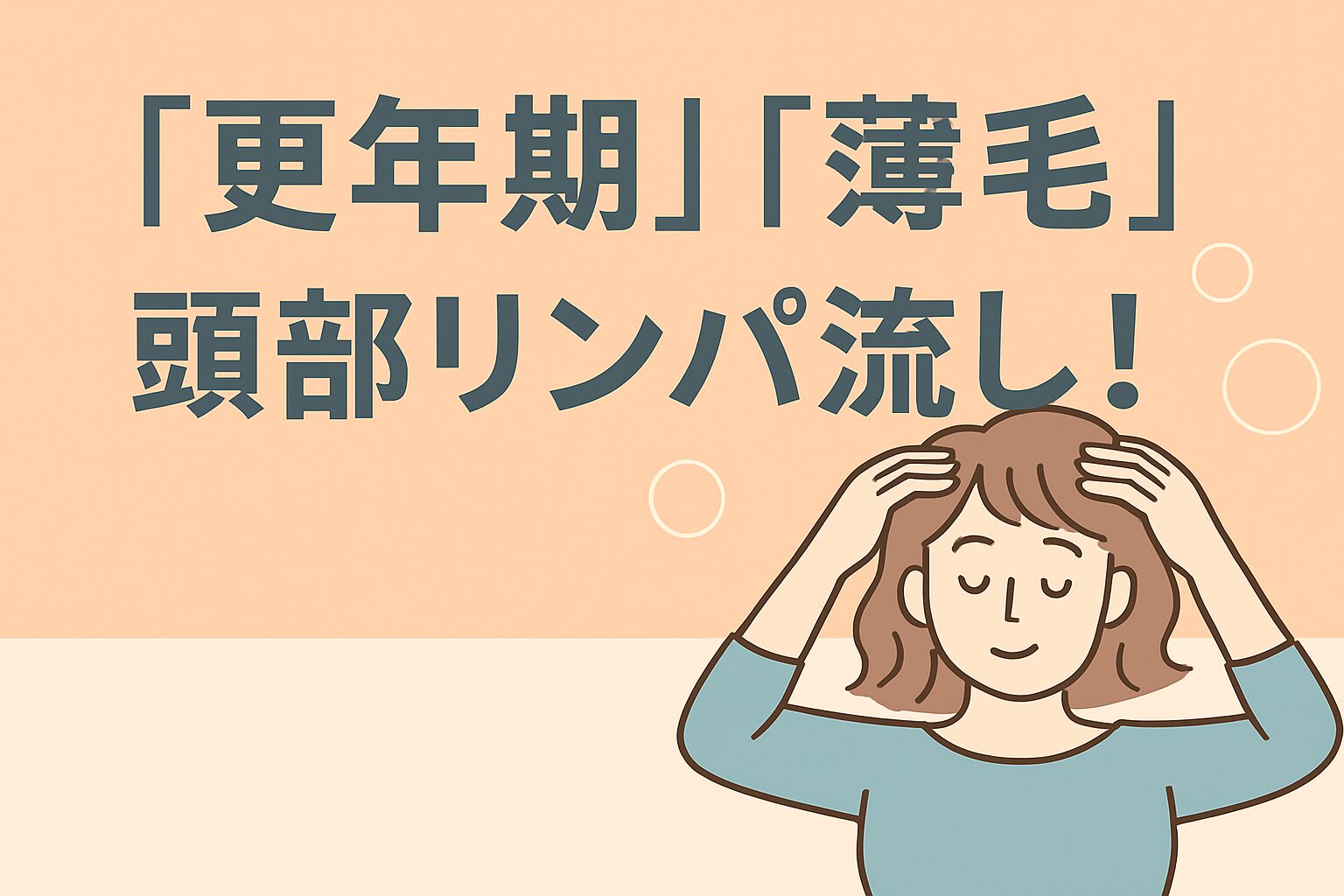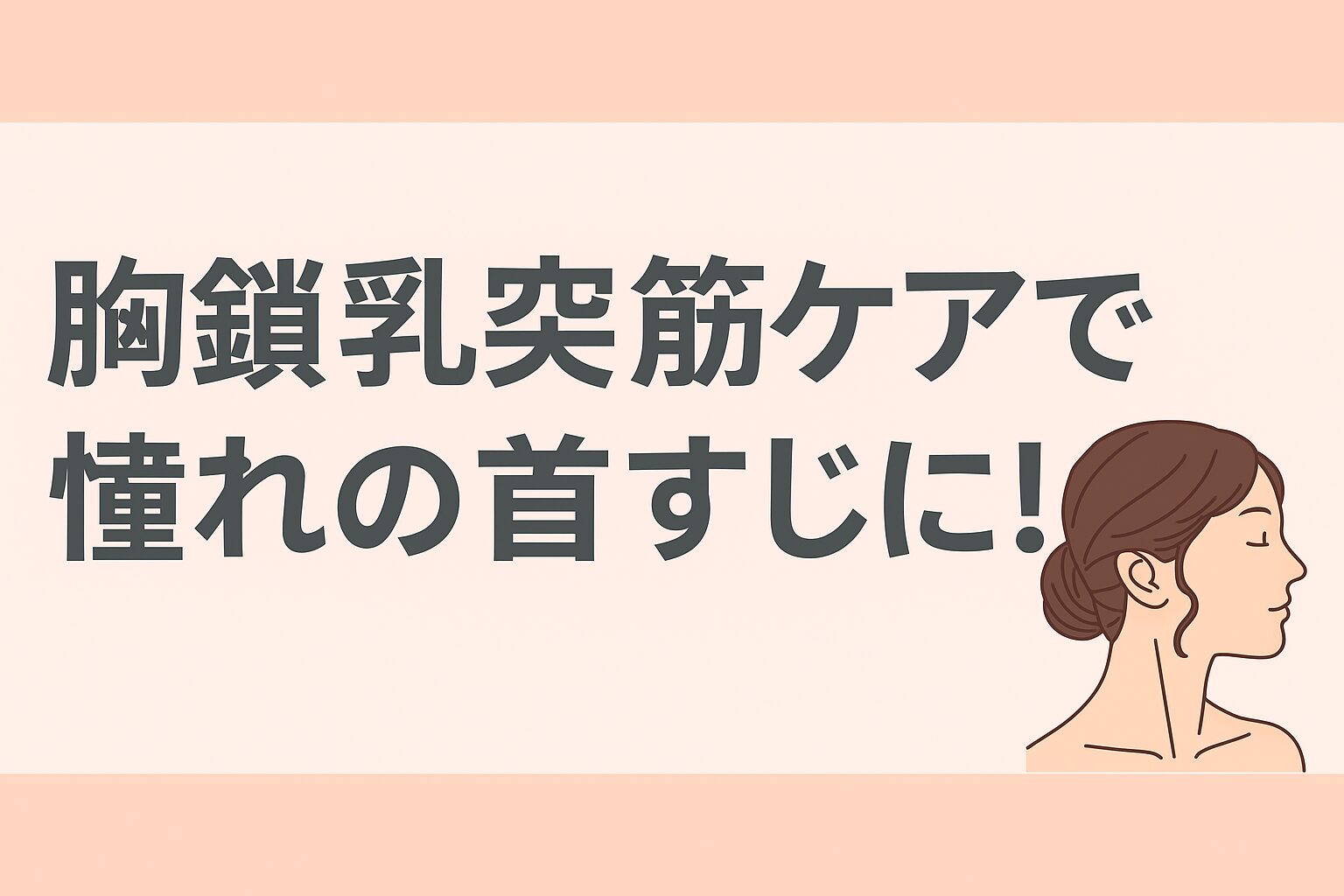更年期の「なんとなく不調」に。『肩甲骨リセット』実践レビュー
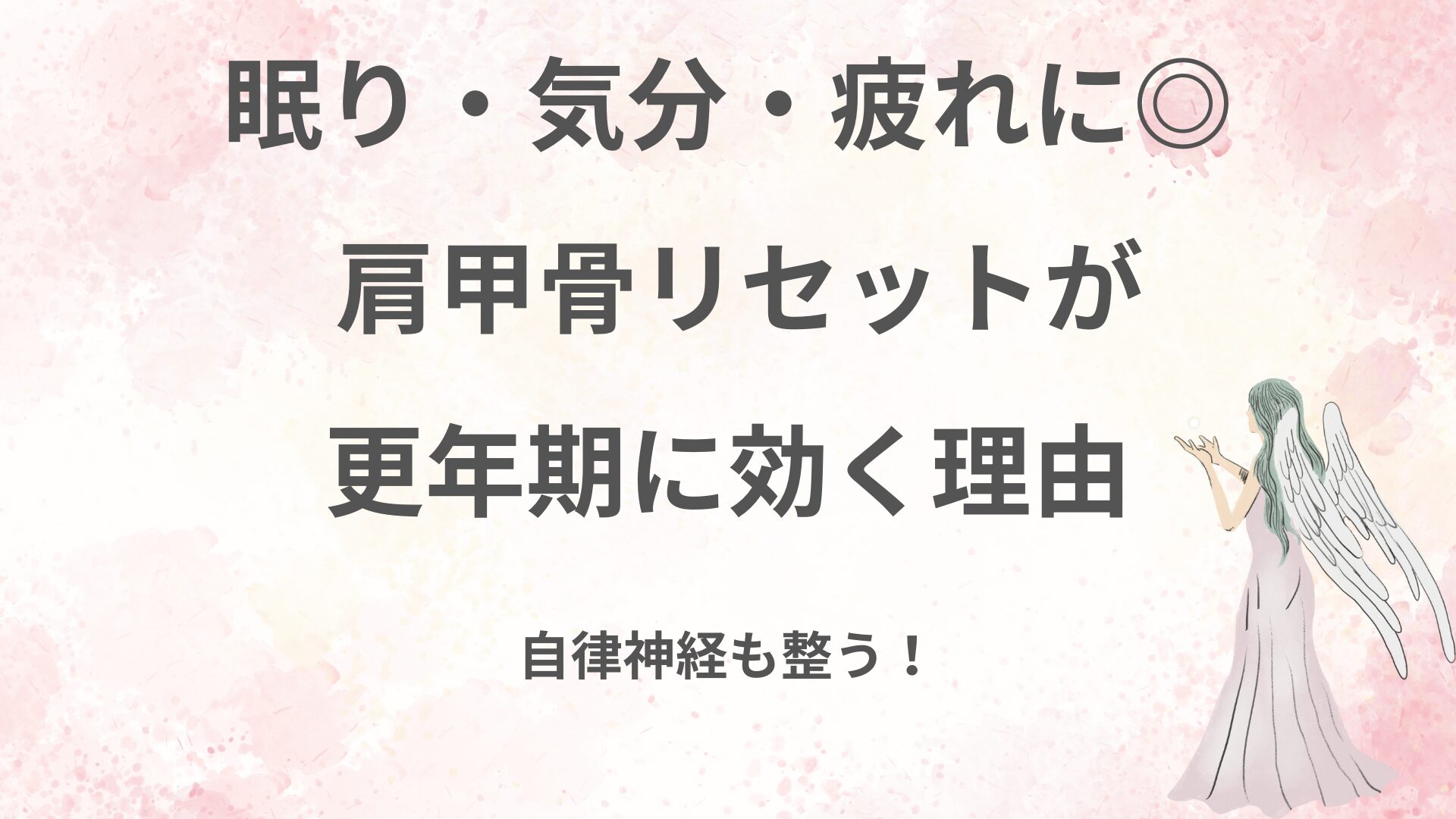
更年期の「なんとなく不調」に。『肩甲骨リセット』(根来秀行)実践レビュー
肩甲骨を動かすと更年期の不調が軽くなる
更年期に入ると、理由のはっきりしない疲れやイライラ、眠りの浅さなど「なんとなく不調」が増えがちです。私は夜中に「カッ!」と覚醒することが起こるようになりました。覚醒した瞬間はなんとも言えない不安感に押しつぶされそうになります。あの恐怖はいったいどこから来るのでしょうか。精神的にも肉体的にもとてもストレスです。
そんなときに出会ったのが『肩甲骨リセット』(根来秀行 著)という本。肩甲骨まわりを意識して動かすことで、めぐりや自律神経のバランスがととのいやすくなり、体も気分も軽く感じられるという内容です。
実際に取り入れてみると、少しずつ姿勢や呼吸のラクさに変化を実感。今では「肩甲骨は健康のスイッチ」と感じるようになりました。
なぜ肩甲骨が大切なのか?
著者の背景と研究の観点
『肩甲骨リセット』の著者・根来秀行先生は、ハーバード大学やソルボンヌ大学で研究に携わった医学博士です。専門は「睡眠」「自律神経」「血流」といった分野で、長年にわたり世界的な研究機関で実証を積み重ねてきました。本書では、その研究成果を日常生活に落とし込み、誰でも簡単に実践できる形で「肩甲骨を動かす重要性」を伝えています。
ハーバード・ソルボンヌ大学の研究から
ハーバード大学では、肩甲骨まわりを動かすことで副交感神経が優位になり、リラックス効果や睡眠の質の改善につながることが確認されています。ソルボンヌ大学の研究では、肩甲骨を中心にした運動によって血管機能が改善し、全身の血流が促進されることが示されています。
更年期世代はホルモンの変化で自律神経が乱れやすく、眠りの質が下がったり気分の浮き沈みが増えやすい時期です。その乱れをサポートしてくれるのが、意外にも「肩甲骨」だと知ると、確かに納得できます。
肩甲骨が固まると起きる不調
肩甲骨が固まると、肩や首のこりだけでなく、呼吸が浅くなり酸素不足から疲労感が強まります。血流が滞ることで冷えを感じたり、自律神経の乱れからイライラや不眠にもつながるとされています。悪循環ですね。
更年期世代の「なんとなく不調」──疲れやすい、頭が重い、寝てもスッキリしない──。これらはホルモンの影響だけでなく、肩甲骨まわりの硬さが関係している可能性があるのです。
実際にやってみて感じた変化
肩のゴリゴリがなくなる!
本書の動きは椅子に座ってできるシンプルなものが中心。1セットを3回繰り返すのですが、初回は肩を回すとゴリゴリ鳴るのに、2回目・3回目と進むほど音が小さくなり、肩まわりがふっと軽くなる実感があります。これは体操をやり始めてすぐに実感しました。肩が軽くなった!という実感です。
左の肩甲骨に「変化の芽」
四十肩を乗り越えた後、右の肩甲骨は羽のように出るのに、左は埋もれて出っ張らないことに気づきました。四十肩を克服して早2年。もう痛みはなく、肩の可動域もまったく問題ありません。しかし左の肩甲骨が出ていない、この左右差が気になる……。ずっとその状態でしたが、この本の体操を3か月ほど継続。いま、左の肩甲骨の縁に指が少し引っかかるようになってきました。ちょっと出っ張るようになってきたんです!左右対称までは時間がかかりそうですが、埋もれていた部分が動きはじめた“兆し”は、続ける力になります。
続けやすいから、習慣になる
- 場所を選ばない:椅子に座って数分でOK(朝TVを見ながら、仕事の休憩時間、寝る前のベッドの上)
- 運動が苦手でも:反動をつけず、呼吸と合わせてゆっくり動かすだけ
- 体調の波に合わせて:回数より「毎日少し」を優先。しんどい日は1セットだけでも可
肩甲骨リセットは誰におすすめ?
痛みがなくても“予防”になる
私は肩こりや腰痛に強く悩んでいるわけではありません。それでも、肩甲骨を動かすだけで左右差の改善に手応えが出てきました。はっきりした症状がなくても、将来のための“体のメンテ”として取り入れる価値があります。
更年期の「なんとなく不調」に寄り添う習慣
更年期は、睡眠・気分・体力の土台がゆらぎやすい時期。肩甲骨ケアは、呼吸の深さやめぐりの良さ、自律神経の安定をサポートするやさしい習慣です。左右差は一朝一夕では埋まりませんが、少しずつでも変化は積み上がります。私も引き続き続けて、変化のレポートを更新していきますね。